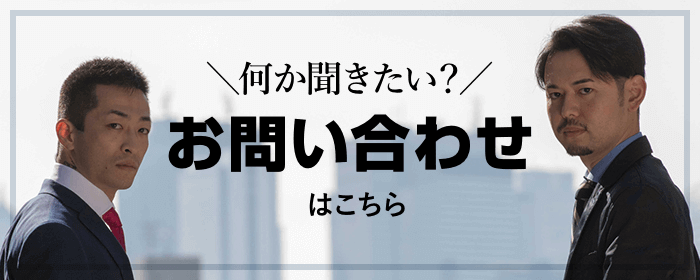「仕事を辞めたいけど産休を取りたい…」辞める前に取るべき5つの対策を解説
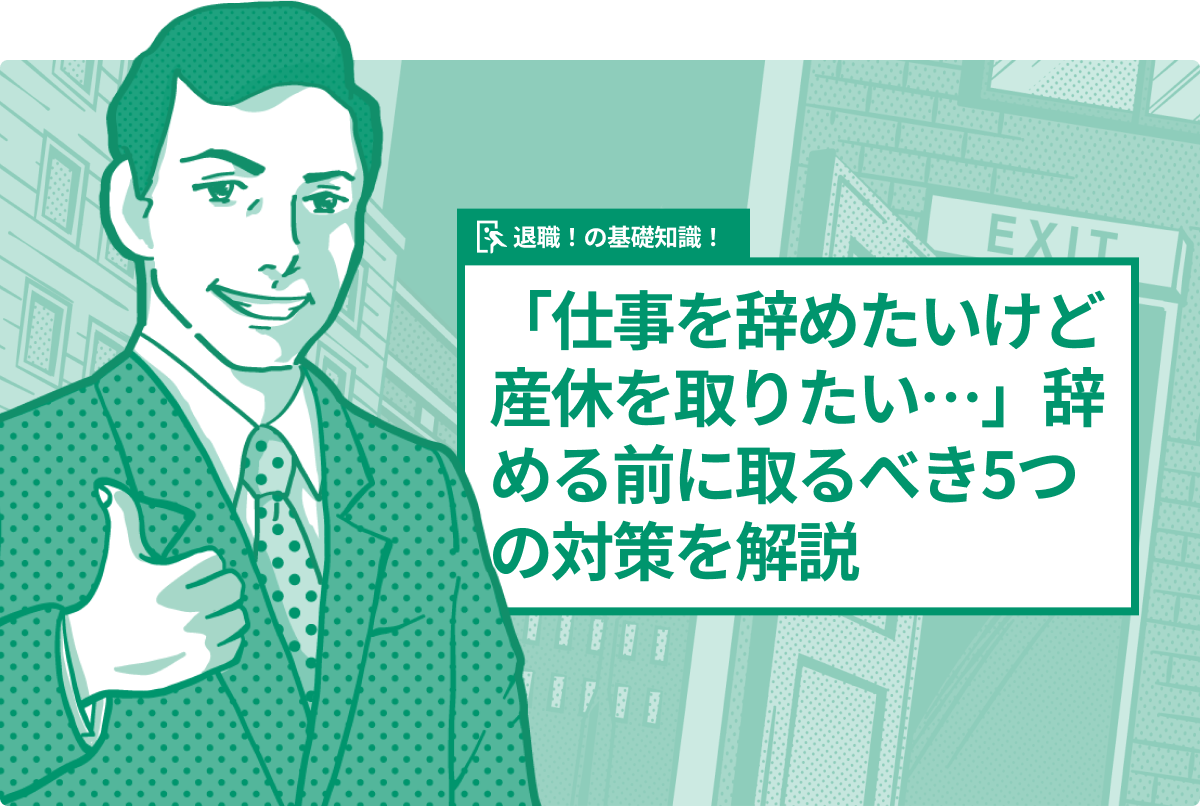
最終更新日 2025年5月24日
「仕事を辞めたいけど産休を取りたい」と悩む方の多くは、どちらの選択肢が良いか決断が難しいのが実際のところです。また、産休後に退職をして問題ないのか、転職してすぐ育休が取れるのか、悩む方もたくさんいます。
結論からいえば、産休を取得後に退職しても問題ありません。とはいえ、金銭的な部分や、もし産休後に仕事に戻った場合の人間関係など、不安がつきないでしょう。
この記事では、仕事を辞めるか産休を取るかでよくある不安・困りごとと対策法について解説します。また、決断するうえでの注意点も解説するので、選択肢を決めるための参考にしてください。
妊娠きっかけで仕事を辞めたい場合は配偶者と話し合いを

妊娠がきっかけで仕事を辞めたい場合は、配偶者と話し合いをして決断することが大切です。あなたの気持ちだけで決めてしまうと、のちにトラブルへと発展しかねません。
また、どの選択肢を取ったとしても、配偶者の協力ありきです。そのため、まずは悩んでいる事実をしっかりと伝え、選択肢を出し合ったうえで決断していきましょう。
産休を取りたい場合取得後に退職も問題はない
基本的に、産休を取得後に退職しても問題ありません。「会社に迷惑をかけてしまうのでは」と不安に感じるかもしれませんが、辞めるのは労働者の自由です。
また、法律においても、労働者の退職は本人の自由とされています。以下は、民法627条の雇用についてです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法627条
例え就労規則に「産休後に退職できない」と記載があっても、法律が適用されます。よって、辞めることに関しては問題ありません。
とはいえ、決断するのに不安はつきないでしょう。次でよくある不安・困りごとを紹介するので、自分と照らし合わせながら決断材料として参考にしてください。
産休前に退職するメリット
産休を取得する人も多い中、あえて産休を取得せず、産休前に退職するメリットとして3つのことがあげられます。
- 妊娠や出産に専念できる
- 仕事のストレスから解放される
- キャリアの見直しができる
ここからは産休前に退職する3つのメリットについてご紹介します。
妊娠や出産に専念できる
産休に入ったら休暇中なので、本来その期間は仕事から解放されます。しかし、産休に入るまでに引継ぎがうまくいっていなかったり、その人にしかわからないことがあったりした場合は連絡が入ることも十分に考えられます。
職場からの連絡が頻繁にあれば、安定期を迎えているとはいえ、「ストレスによってお腹の中の赤ちゃんに影響がないか」と不安になるほか、「出産直前まで連絡が来るのか」など心配になっても不思議ではありません。出産に専念すべきところなのに、産休中はなかなか専念できないことも十分に考えられます。
仮に退職してしまえば、会社からの連絡は入らなくなるでしょう。赤ちゃんを元気よく産むことに専念したい場合に産休前の退職は選択肢として有力です。
仕事のストレスから解放される
休みに入る前はバリバリ仕事を働いていて、さほど忙しさに疑問を抱いてこなかった人ほど、まとまった休みを経験すると、「もう復帰したくない」という気持ちになりがちです。
いざ休みに入ると時間を有効活用できるようになります。例えば、今まで行ってきた仕事がとても疲れる仕事で、ストレスも相当たまっていたことを自覚した場合、「またあの現場に戻るのか」と不安になる人は多いでしょう。
しかも、仮に復帰するとなれば子育てをしながらの復帰なので、子育てとの両立ができるのか心配になる方も出てくるでしょう。時間に余裕ができるからこそ、仕事のストレスからも解放されるわけですから、産休前の退職は十分なメリットがあると言えます。
キャリアの見直しができる
バリバリ仕事をこなしている間は、将来的なことをあまり考えることなく、目の前の仕事を追いかけ続けるものです。妊娠し、出産までの期間は今までの仕事量をセーブし、時間にも心にも余裕が生まれるでしょう。その際に、将来的なことを考える時間ができます。
今までのキャリアを見直すには絶好の機会であり、「今のまま働き続けた方がいいのか」、「もっといい場所で働けるのではないか」など色々なことを思うようになります。キャリアの見直しができる時間を設けるために産休前に退職するのもおすすめです。
諸外国では出産後すぐに復帰するケースもありますが、それだけ出産後のシステムが行き届いているからです。それらのシステムが行き届いていない場合はすぐに復帰するのも大変でしょう。どのみち復帰するまでに時間がかかる以上、今までを振り返り、出産をきっかけに新しいことにチャレンジしたいという考えはアリです。
仕事を辞めるか産休を取るかでよくある5つの不安・困りごと

仕事を辞めるか、産休を取るかでよくある不安・困りごとは以下の通りです。
- 金銭的に不安
- 産休後に今の職場の人間関係で働けるか不安
- 再就職できるかわからない
- 仕事内容がつまらない
- お腹の赤ちゃんの影響
いずれにしても、今の職場から一旦離れる事実は変わりません。今までと環境が変わるので、現実的にも精神的にも不安がともなうでしょう。
また、よくあるケースを見ることで、考えていなかったリスクも見えてくるはずです。それぞれの不安・困りごとについて、以下で詳しく解説します。
金銭的に不安
仕事を辞めてしまうと給料がなくなるので、金銭的に不安を抱えている人は多いです。また、産休手当がない会社でも、同様の不安を抱えている人がたくさんいます。
生活が苦しくなれば、子育てのための貯金も難しくなるでしょう。加えて、配偶者の給料によっては「貯金を切り崩さないと」と悩む人も少なくありません。
妊娠・出産における金銭面の負担を減らす方法に「出産手当金」や「出産一時支援金」といった制度があります。制度を利用することで、今後の選択がしやすくなるでしょう。
2つの制度については、下記で詳しい概要を解説しています。ぜひ一度目を通してみてください。
産休後に今の職場の人間関係で働けるか不安
今の職場の人間関係に悩んでいる人は、産休後により一層働きづらくならないか不安を抱えているケースが多いです。
そもそも、人間関係が良好じゃない限り「産休を言い出しにくい」という人がほとんどでしょう。加えて、産休を良く思わない人もいます。プラスしてすでに人間関係が悪いなら、不安を抱えるのは当然です。
ただ不安が大きいのであれば、辞める選択肢が良いかもしれません。復帰後に人間関係が良くなる保障がないからです。
これから子どもが産まれてくるうえで、子育てに支障をきたす可能性も出てきます。ストレスで体を壊してはせっかくの産休が台無しになるので、何のために休暇を取ったのか考えたうえで決断してみましょう。
再就職できるかわからない
仕事を辞めるか産休を取得するかで悩む人の中には、仮に仕事を辞めた場合に再就職ができるかどうかへの不安を抱えている人がいます。産休前に退職し、出産後一定の期間は子育てを行ったとすれば、1年程度休むことになります。社会人として1年間のブランクがあるというのは、結構不安に感じる部分です。
特に、繁忙期があって忙しくなりやすい職種の場合には、「子供をどこに預け、どれくらい働けるものか」と不安になってもおかしくありません。こうした不安があると再就職できるかどうかという悩みにつながりやすくなります。
今までのキャリアをどのように捉え、今までのことを活かす仕事がしたいのか、全く異なるしごとがしたいのかなど、これまでのキャリアを振り返った上でキャリアを継続するかどうかを考えてみましょう。
仕事内容がつまらない
仕事内容がつまらないから、産休を機に辞めたいという人も意外と多いです。事実、仕事にやりがいがなければ苦痛でしかないので、ある意味当然なのかもしれません。
加えて、辞めると会社に伝えるには、きっかけがないと言い出しにくいものです。仕事がつまらないことが前提にあり、なおかつ産休が重なればむしろ良いタイミングといえます。
実際に、辞めずに会社に復帰したとしても、同じ理由で退職したいと考えてしまうでしょう。ただし、次は理由が「仕事がつまらない」だけになってしまいます。
結果的に「仕事を辞めたいけど言い出しにくい」の繰り返しになるだけなので、どこかで踏ん切りをつけることが大切です。
お腹の赤ちゃんの影響
結局のところ、妊娠してしまうと自分のことよりもまずは赤ちゃんのことを考えるようになります。お母さんが感じるストレスなどがお腹の赤ちゃんに影響を与える可能性は十分に考えられるでしょう。これ以上ストレスをお腹の赤ちゃんにかけたくない場合に、仕事を辞めるか産休を取得するかで悩むことがあります。
仕事を辞めればストレスから解放されますが、今度は仕事を辞めて収入はどうなるのかといった新たなストレスが襲い掛かる場合があります。そのあたりのストレスをどこまで考慮して、決断を下せるかが問われるでしょう。
妊娠がきっかけで仕事を辞めたい場合の7つの対策

妊娠がきっかけで仕事を辞めたい場合の対策法を紹介します。
- 妊活時期をずらす
- リモートワーク可能か相談してみる
- 副業を視野に入れておく
- 辞めた後の転職先で育休を取る
- 失業手当(失業給付金)の申請をする
- 出産手当金の申請をする
- 出産一時支援金の申請をする
前提として、人間関係や仕事がつまらなくて辞めたい場合は、退職の決断をするのが一番の対策法です。繰り返しますが、一度辞めたいと感じてしまったら、復帰後にも同じ心理になってしまいます。
とはいえ、配偶者との話し合いのなかで、辞めない選択を強いられるケースもあるでしょう。その際には、ここで紹介する対策法を伝えると、理解を示してくれるかもしれません。
それぞれの対策について、以下で詳しく解説します。
妊活時期をずらす
妊活時期をずらし、先に仕事を辞めてしまうのも選択肢の1つです。そうすれば、会社に迷惑をかける心配がなければ、退職後に妊活に専念ができます。
また、出産して子育てが落ち着いてから、別会社に転職することも可能です。今の職場でのストレスもなくなるので、先に不安を解消したいならアリでしょう。
ただし、妊娠前に辞めてしまうと、出産手当金はもらえません。金銭面に不安のある方は、しっかりと考えたうえで決断してください。
リモートワーク可能か相談してみる
毎朝の通勤はサラリーマンやOLにとっては相当な負担になりえます。満員電車に揺られ続けるのはあまり気分のいいものではありません。特に妊娠中はただでさえ疲れやすく、まして安定期ではない時期は相当大変です。
このため、リモートワークで仕事をすることは可能かどうかを相談してみることをおすすめします。リモートワークであれば通勤の時間は必要ありませんし、急に体調を崩してもすぐに横になれる環境があるので安心です。
妊娠中はホルモンバランスも崩れやすく、体調面も不安定になりやすいからこそ、リモートワークを通じて仕事ができるのが理想的です。
副業を視野に入れておく
本業だけの収入で生活している人も当然いますが、副業を行うことで稼ぎを増やす人もいます。同時に、会社から理不尽な対応をされた場合に副業があれば大きな気分で対処できるでしょう。今のうちに副業を視野に入れておくことで、万が一の時の選択肢になりえます。
自分で稼ぐ力をつけられれば、自信になるほか、再就職が難しそうでも自分で何とかできるようになるので不安な気持ちを抑えることができます。副業を視野に入れ、自分で稼ぐ力をつけてみるのもいいでしょう。
辞めた後の転職先で育休を取る
辞めた後の転職先で育休を取る方法もあります。育休は「育児・介護休業法」の法律で定められた制度なので、申請すれば男性・女性問わず取得可能です。
ただし、会社が労使協定を結んでいる場合、雇用されて1年未満の人は取得できません。また、原則として0歳から1歳までの子どもの場合のみ認められます。
一方で、産休は雇用期間の定めなく、誰でも取得可能です。よって、産休取得後、雇用期間が1年経ってから育休を取れば、特に問題はありません。
とはいえ、妊娠を隠したまま転職し、計画的に産休・育休を取得すると、良い顔はされないでしょう。そのため、転職時に申し出ておくことが大切です。
失業手当(失業給付金)の申請をする
退職後に失業手当の申請をすると、金銭面の負担が軽減できます。雇用保険の被保険者期間が、離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上あれば、誰でも受け取りが可能です。
ただ失業手当は、就職する意思と能力がある人に与えられた制度になります。そのため、妊娠・出産を理由に退職をした場合は、就職できる能力がないと判断されてしまうので、すぐには受け取れません。
とはいえ、妊娠・出産の場合は特例措置があり、退職日して31日経過後から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」を提出すれば、最長4年まで延長が可能です。
よって、今の職場を辞めた後に延長申請をし、出産・育児が落ち着いてから就職活動をする際に受給申請をすることで、失業手当の受給が可能となります。
ハローワークで申請ができるので、退職前に一度相談してみてください。
出産手当金の申請をする
出産手当金とは、産休・育休取得後に今の職場から給料が出ない場合に支給される制度です。金銭面の負担が軽減されるので、選択肢の1つとして踏まえておきましょう。
出産手当金を受給できる条件は、以下の通りです。
- 会社の健康保険に加入している被保険者
- 妊娠してから4ヶ月(85日)以降の出産
- 出産を理由に休業
会社が加入している健康保険から支給されるので、国民健康保険への加入者は対象外です。また、本人が被保険者のみ受給対象となり、配偶者の扶養で加入している場合は受け取れません。
1日あたりの支給金額は、遡って12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3となります。適用期間は、出産予定日42日前から出産後56日目までの98日間です。
申請する場所は、会社が加入している社会保険事務所になるので、詳しい内容は一度問い合わせてみてください。
出産一時支援金の申請をする
出産一時支援金とは、会社の健康保険、または国民健康保険に加入している女性が出産した場合に受給できる制度です。
出産一時支援金の場合は、被保険者でも扶養者でも支給されます。金額は1人の子どもあたり50万円(双子だと100万円)と大きいので、金額の負担がより一層軽減されるでしょう。
また、申請する場所は、会社が加入している社会保険事務所となります。国民健康保険の場合は、市役所にて申請が可能です。
出産翌日から2年間は受給できるので、忘れずに申請しましょう。
妊娠がきっかけで仕事を辞めたい場合の3つの注意点

妊娠がきっかけで仕事を辞めたい場合の4つの注意点について解説します。
- 有給は消化しておく
- 同僚・上司に伝えておく
- 引継ぎ業務をしておく
- 保育園に入れない可能性がある
事前に注意点を把握しておけば、その後のトラブル防止につながります。円満退社をするためにも、目を通しておきましょう。
有給は消化しておく
産休中でも有給は消化できますが、産後8週間以内は使えません。もし産休後に辞める決断をした場合、有給が消化できないまま退職になるので注意が必要です。
また、出産手当金と同時に有給消化も不可となっています。そのため、金銭面の負担を軽減させるために、事前に有給の計画を立てておくことが大切です。
選択肢の1つとして、産休に入ってから有給を消化し、その後に退職という方法があります。仮に退職しなかったとしても、産休中の負担軽減につながるので、計画を立てたうえで最善の選択肢を取ってください。
同僚・上司に伝えておく
同僚・上司には、産休を決断した段階で伝えておいた方が良いです。加えて、退職しようと考えているなら、一緒に伝えておきましょう。
いずれにしても、理解を得られた状態なら大きなトラブルにはなりません。さらに、妊娠後はつわりや体調不良などが出てくるので、伝えておくだけで周りの配慮は違います。
また、早期に伝えておくと、円満退社がしやすくなるでしょう。人間関係で悩んでいる方は言い出しにくいかもしれませんが、勇気を出して伝えることで、残りの期間働きやすくもなるはずです。
引き継ぎ業務をしておく
引き継ぎ業務は忘れずにしておきましょう。引き継ぎをしないまま辞めてしまうと、会社に迷惑をかけるのはもちろん、「業務がわからない」と連絡が来るかもしれません。
また、引き継ぎ業務はなるべく早めにしておくことが大切です。もし産休直後までしないままにしておくと、急な体調変化があったときに対応できなくなります。
今の職場での最後の仕事になるので、感謝の気持ちを込めて引継ぎ業務を行いましょう。
保育園に入れない可能性がある
出産後、仕事を辞めたい場合に注意したいのは、保育園に入れない可能性があることです。例えば、認可保育園の場合は保護者が働いていることが条件になっている場合があります。そのため、会社を辞めることで就労していないと判断され、入れない可能性が出てきます。
幼稚園であれば特に問題はないものの、0歳児や1歳児を扱う幼稚園はほとんどありません。0歳児や1歳児を預けられるところを確保しておかないと後々大変なことになるでしょう。
まとめ

今回は、「仕事を辞めたいけど産休を取りたい」と悩む方に向けて、よくある不安・困りごとと対策・注意点について解説してきました。
今の段階で仕事を辞めたいと考えているなら、退職するのも選択肢の1つです。仮に、産休後に復帰したとしても、同じ悩みが繰り返されるかもしれません。
また、子どもが産まれて子育てをしていくなかで、仕事のストレスを抱えてしまうと、悪影響を及ぼす可能性もあります。大切な授かりものである子どものためには、どちらの選択肢が良いかしっかりと考えていきましょう。