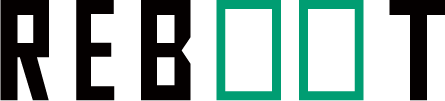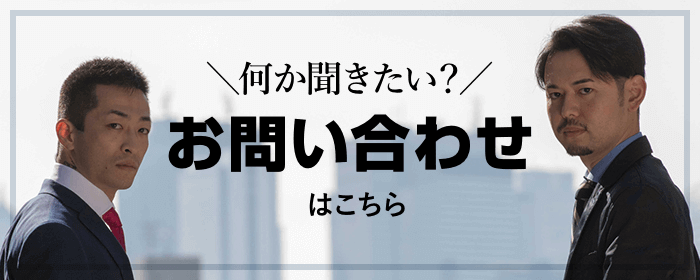退職代行を使うと退職金はもらえない?退職金をもうらための対応策
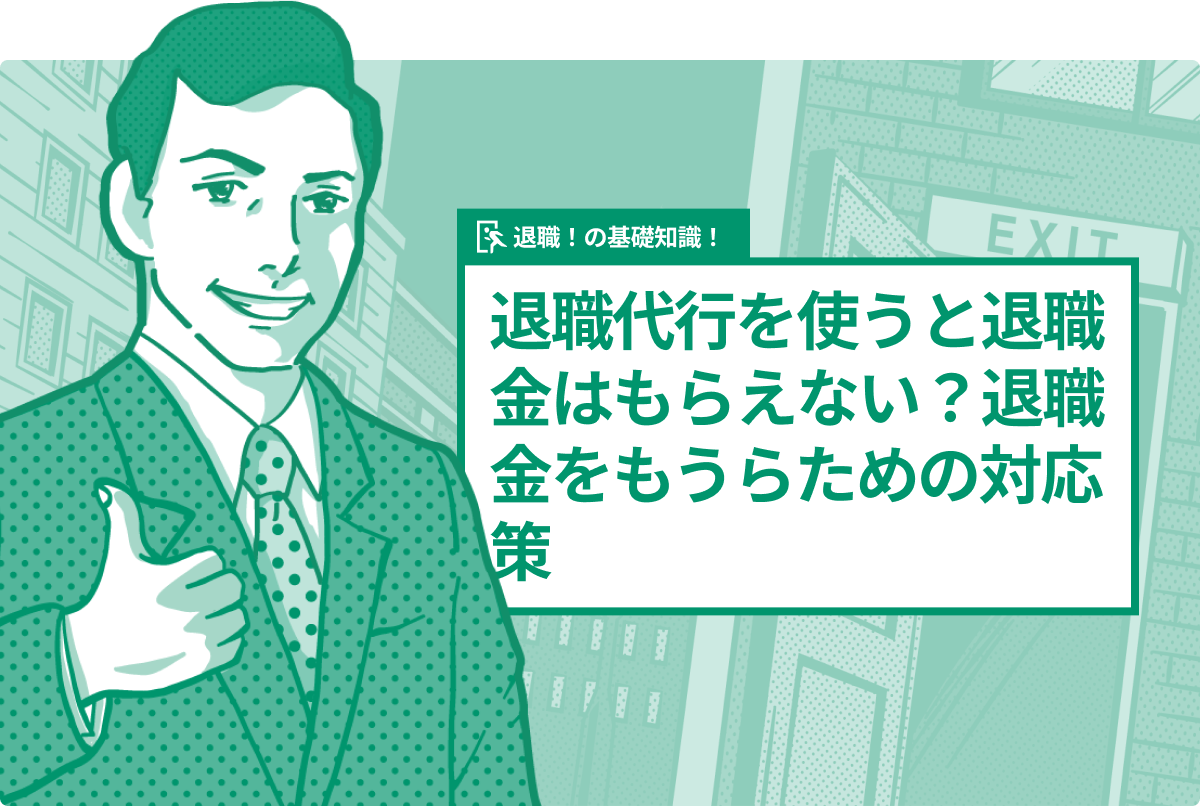
最終更新日 2023年7月12日
「退職代行を使うと退職金はもらえない?」と不安な方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、退職代行を利用した場合でも退職金は支給されます。ただ、会社の退職金支払いは義務ではなく、場合によっては減額や不支給となる可能性があるため注意が必要です。
今回は、退職代行で会社を辞めた際に退職金をもらえないケースと対応策についてご紹介します。
本記事を読めば、退職金がもらえない場合の理由や具体例について理解し、自分は支給条件を満たしているのかを判断できるでしょう。また後半では退職金以外にもらえる給与・手当や、弁護士と労働組合に依頼するメリット・デメリットについて解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
退職代行で辞める前に!退職金の基礎知識
退職代行で会社を辞める前に、退職金をもらいたい依頼者が押さえておくべき「基礎知識」について解説します。
退職金の概要と制度の種類
そもそも退職金とは、従業員が退職する際に会社からもらえる金銭のことです。また、退職金を支払う制度のことを退職金制度と呼びます。定年退職する労働者だけでなく、転職や解雇、逝去した従業員も対象となることがあります。
一般的な退職金制度の種類は、以下の通りです。
- 退職一時金
- 確定給付企業年金
- 中小企業退職金共済(中退共)
- 企業型確定拠出年金(DC)
基本的に本人が勤務する会社によって、退職金制度の種類や受け取れる金額などが異なるのでチェックしておきましょう。
会社の退職金の支払いは義務ではない
会社に退職金の支払いを義務化する法律はありません。会社が退職金制度を導入していなければ、退職代行を使う・使わないに関わらず、支給されることはありません。
一方、会社が退職金に関する規定を明示している場合、支払いの義務が発生します。具体的な記載内容の例は以下の通りです。
- 退職金をもらえる労働者の範囲(勤続年数や雇用形態の条件など)
- 不支給の決定や減額の条件、計算方法
- 一時金・年金扱いなどの支払い方
- 支払われる時期
詳しい内容は、会社の退職金規定に記載されているので、気になる方はチェックしてみてください。
退職金制度がある企業の割合
厚生労働省によると、退職金制度がある企業の割合は全体で「80.5%」です。また、企業規模別の導入率は、以下のようにまとめられます。
| 企業規模 | 退職金制度の導入割合 |
| 30~99人 | 77.6% |
| 100~299人 | 84.9% |
| 300~999人 | 91.8% |
| 1,000人以上 | 92.3% |
従業員数が多いほど、退職金制度を導入している企業の割合は大きいことがわかります。
会社規模が小さい場合、退職金制度がないケースもあるので、事前にチェックしておきましょう。退職金をもらえなくとも、有給休暇や未払いの給与、残業代、失業手当は受け取れる可能性が高いです。退職金以外にもらえる給与や手当については、下記で詳しく解説します。
退職代行を利用した際に退職金をもらえないケース
退職代行を利用した際に、退職金をもらえないケースとして、以下の例があげられます。
就業規則に退職金支給について記載がない
就業規則に退職金についての規定がない場合、退職代行の利用に関わらず、基本的に退職金はもらえないでしょう。
また、退職金制度によっては自分で積み立てを負担する場合もあります。積み立て式の退職金制度を導入している企業であれば、給与明細に「企業年金掛金」「退職金掛金」と控除金額が記載されているので確認してみましょう。
退職金の支給条件を満たしていない
退職代行を使用した際、退職金の支給条件を満たしていないと、基本的にもらうことはできません。
例えば、会社の退職金規定に「勤続年数3年以上」と記載されている場合、入社してから3年未満の従業員は、退職金が不支給となります。他にも、「無断欠勤の繰り返しや懲戒解雇扱いは不支給」といった条件が記載されていることも多いです。
退職金の支給が慣例的ではない
退職代行を利用した際に退職金がもらえないケースとして、支給が慣例化されていない場合があげられます。
原則、就業規則に退職金規定がない場合、退職金を請求することはできません。しかし、就業規則に記載がなくても、退職金の支給が慣例的である場合、会社に支払い義務が生じる例外のケースがあります。
例えば、毎年退職する従業員に対して退職金を支給しているのにも関わらず、自分が会社を辞める際に支払われなかったケースです。この場合、継続的に退職金を支給していた証拠を提示できれば、労働者は会社に請求できる可能性が高まります。
ただ、一部の功労者だけ受給していたり、慣例を証明できなかったりすると、請求が難しくなるので注意が必要です。
退職代行で辞める際に退職金をもらうための準備
退職代行で会社を辞める際、退職金をもらいたい方は就業規則をチェックしておきましょう。「どの制度を採用しているか」「どのくらいもらえるのか」は、就業規則や賃金規定を見ればスムーズに確認できます。
退職金規定がある場合、会社によって支給条件は異なり、自分が対象となるかは確認する必要があります。就業規則の確認方法がわからない場合は、会社の人事労務担当者に問い合わせましょう。
また、退職金の支払い拒否に対抗するためにも、支給条件を満たす証拠を集めておくのが有効です。具体的には、勤続年数がわかる書面や給与明細、雇用時の契約書などがあげられます。
退職代行の利用で後悔しないためにも、万全に準備しておきましょう。
退職代行の利用後に退職金が未払い・支払われない場合の対応策
退職代行を利用した際、退職金の支給条件を満たしているのに、会社から支払われない場合の対応策として、以下の例があげられます。
会社に請求書を送付する
退職代行の利用後に退職金が支払われない場合、会社に請求書を送付できます。会社に対して請求したことを証明するためにも、内容証明郵便の利用がおすすめです。
内容証明郵便を利用すれば、送付した日時や相手、請求書の内容を証明してくれます。請求した事実を残しておけば、会社から手続きを放置されるリスクが防げるでしょう。未払い退職金の時効は、労働基準法115条で「5年」と定められているので注意してください。
労働局や労働基準監督署に相談する
退職代行で辞めた後、請求書を送付したにも関わらず退職金をもらえない場合、最初の相談先として労働局や労働基準監督署がおすすめです。
労働基準監督署などに相談すれば、支払いを放置・拒否された後に取るべき行動や利用する制度などのアドバイスをもらえます。
ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
退職代行で辞めた後、退職金の支給を会社から不当に拒否された場合、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討しましょう。ADRとは、訴訟をせずに労働紛争の早期解決を図る方法です。
裁判と比較すると手続きが迅速・容易で、費用が安く済む場合があるというメリットがあります。また、関係者以外には非公開となるので、退職代行を利用した情報が転職希望先に漏れるリスクも抑えられます。
弁護士に相談する
ADRを利用しても退職金の未払いが解決できない場合は、弁護士に相談してみましょう。費用はかかりますが、弁護士は法律のプロであり会社との交渉もできるメリットもあります。
また、弁護士から退職金を請求されたという事実を会社側に示すことで、心理的に優位な状況に持ち込めるでしょう。
退職代行でもらえる退職金以外の給与・手当
退職代行を利用した場合でも、退職金以外にも以下の給与や手当をもらえます。
未払い給与
未払い給与は、退職した後でも請求することが可能です。未払い給与が発生するパターンとして「会社の業績不振が原因で給料が支払われない期間があった」などがあげられます。
退職代行の利用に関わらず、未払い金は請求できるため安心してください。退職金の請求と同様に、未払い給与を証明できる証拠と請求書を内容証明郵便で送付しましょう。
残業代
退職後は、退職金と未払い給与と同様に、残業代も請求できます. 未払いの残業代があれば、支払われていない証拠を用意し、請求書を内容証明郵便で送付しましょう。
有給休暇
退職代行を使って辞めた場合でも、残っている有給休暇は消化できます。なぜなら、有給休暇の日数や期間は労働基準法によって定められ、会社が勝手に調整することはできないからです。
有給休暇を活用すれば、正式な退職日までの期間は欠勤扱いになりません。欠勤扱いになるとトラブルが起こる可能性もあるので、有給休暇が残っている方は、申請を忘れないように覚えておきましょう。
失業保険
退職代行を利用すると、基本的に自己都合の退職となるケースが多いため、失業保険の受給開始や給付日数などは少なくなりますが、手当を受け取ることは可能です。
失業保険の手続きを行うには、離職票が必要となるので会社に送ってもらえるように依頼しましょう。
弁護士や労働組合運営の退職代行サービスを選ぶメリット
一般的に、退職代行サービスは運営元が一般企業・弁護士・労働組合に分かれます。ここからは、弁護士や労働組合運営のサービスに退職代行を依頼するメリットをご紹介します。
退職金などの交渉権がある
弁護士や労働組合の退職代行サービスは、会社と交渉する権利を有するため、退職金の支給に関して交渉してもらうことが可能です。
一方、一般企業の代行業者が会社と交渉すると違反行為となるので注意が必要です。ただ、代理人として依頼者の連絡・通知のみを徹底して行えば、間接的に交渉できる場合もあります。
一般企業と比較すると安心感を得られる
弁護士や労働組合の退職代行サービスは、資格を持たない一般企業と比較すると安心感を得られます。そのため、会社から退職金がもらえないなどのトラブルが起こる可能性は低くなるでしょう。
一般企業でも退職サポートの実績が豊富で、弁護士から監修を受けているサービスを安価に提供する場合もあるため、自分の目的に合った退職代行業者を選ぶことがおすすめです。
法的なトラブルに対応しやすい
弁護士の退職代行サービスを利用すれば、法律関係のトラブルが発生しても安心して対応を任せられます。そのため、未払いの給与や退職金などに関して、退職時に徹底的に話し合いたい場合におすすめです。
ただ、裁判を起こすことで、退職が長引いたり心理的負担が大きくなったりすることを避けたい場合は、一般企業の退職代行サービスを利用した方がいいケースもあります。
弁護士や労働組合運営の退職代行サービスを選ぶデメリット
弁護士や組合運営の退職代行サービスを選ぶデメリットは、以下の通りです。
退職金の交渉を依頼すると料金が高くなる可能性がある
弁護士や労働組合の退職代行サービスは、一般企業のサービスと比較すると料金が高くなります。例えば、弁護士に退職代行を依頼する場合、料金相場は5万円〜で、成功報酬が上乗せされるケースが多いです。
また、労働組合のサービスに会社との交渉を依頼する場合、通常料金に追加して組合費2,000円ほど支払う場合があるのです。
一方、一般企業のサービスは2万円〜で低価格で退職代行を依頼でき、追加料金が必要ない場合が多いため、支給された退職金の節約につながります。
土日・祝日に対応できないことが多い
弁護士による退職代行サービスは、土日・祝日などに対応できないことがあります。弁護士事務所の休日にトラブルが発生しても、自分で対処する必要があるのです。
一方、一般企業の退職代行は24時間受付可能なサービスが多く、土日・祝日でも即日で退職手続を進めてくれることがあります。
転職支援などのサービス範囲が少ない傾向がある
弁護士や労働組合の退職代行は、転職支援などのサービス範囲が少ない傾向にあります。弁護士に依頼すると裁判に対処できますが、基本的に転職先を見つけられるサポートは行っていません。
一方、一般企業が運営する退職代行は、退職後の転職支援サポートを提供している場合があります。次の収入源を確保しやすいので、退職金などを転職活動や生活費に使わずに済むでしょう。
退職代行サービス利用時の料金相場
退職代行サービスを利用する際の料金相場は、運営元によって大きく変わります。まずは下記の比較表を確認していきましょう。
| 運営元 | 料金相場 | 対応できる業務 |
| 弁護士 | 5万円~10万円 | 退職の連絡
退職交渉 訴訟時の対応 慰謝料請求 業務引き継ぎの調整 退職届の代筆 |
| 労働組合 | 3万円~6万円 | 退職の連絡
退職交渉 |
| 一般企業 | 1万円~5万円 | 退職の連絡 |
上記を見てもわかるように、価格が高い順に対応できる業務の範囲が広くなります。弁護士に依頼した場合は、退職交渉のほかにも裁判の対応や退職に関する書類の代筆が可能です。
労働組合の場合は、訴訟代理人にはなれません。退職交渉はできますが、あくまでも団体交渉権に基づいた内容のみ対応できることを理解しておきましょう。
一般企業が提供する退職代行サービスは、料金設定がピンキリとなっています。加えて「退職の意志を代わりに伝える」のがサービス内容となっているため、会社側との交渉はできません。
上記の違いを理解したうえで、自分が求める内容に沿った退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行サービスを利用して退職金を得るための手順
退職代行サービスを利用して退職金を得るための手順は、以下の通りです。
- 利用する退職代行サービスを決める
- 退職代行サービスの担当者と打ち合わせ
- 利用料金の支払い
- 退職代行の手続き開始
- 退職届の提出や引き継ぎ・私物の引き取り
- 退職金の受け取り
結論として、退職代行を利用したから退職金を受け取れないということはありません。ただし、退職金を受け取る条件を満たしていることが大前提です。
たとえば就業規則や退職金の規定に支給の定めがなければ、そもそも受け取り対象外です。また、勤続年数や会社が決めた条件を満たしていなければ、支給対象とはなりません。
退職金はあくまでも会社が独自で儲けているものです。規定がなければ、退職金が受け取れないことはあらかじめ理解しておきましょう。
退職代行を利用する際に関するよくある疑問
退職代行の利用を考えている人からは、以下のような疑問があげられています。
- 引き継ぎをする必要はある?
- 貸与品は持っていかないといけない?
- 退職代行の利用は転職に影響する?
- 即日で退職できる?
- 退職代行を使う人はクズ?
- 追加費用が発生する場合はある?
- 退職金の計算方法は?
- 中小企業の退職金の相場は?
それぞれの内容を確認して、退職代行を正しく利用できるようにしましょう。
引き継ぎをする必要はある?
退職代行を利用する場合も、引き継ぎはしておいた方が良いです。業務の引き継ぎは法律で義務化されていませんが、しなければ以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
- 損害賠償の請求
- 退職後の会社・顧客からの連絡
- 懲戒処分扱いにされる
退職代行の利用を考えているなら、1か月前を目安に業務の引き継ぎを進めておきましょう。やめることを伝えるのは難しいため「サポート人員を増やしたい」「自分がいないときでも業務を回せるようにしておきたい」などの理由を用意しておくのがおすすめです。
また、就業規則を確認して義務化されている場合は素直に従っておきましょう。就業規則違反になってしまうと、退職金の支給条件から外れてしまう可能性があります。
貸与品は持っていかないといけない?
会社からスマホやパソコンなどの貸与品が支給されている場合、返却は必ず必要です。ただし、必ず持参する必要はありません。
退職代行を利用して即日辞める場合は、会社に郵送しましょう。送付する際は、元払いにしておけばトラブルにつながりにくいです。
もし事前に辞める準備をしているなら、退職前に持っていけば問題ありません。返却の時期は、業務に支障が出ないタイミングにしましょう。
貸与品を返却しないと、損害賠償請求や情報漏洩を疑われるなどのトラブルにつながります。郵送・持参のどちらでも構いませんので、必ず返却を忘れないようにしてください。
退職代行の利用は転職に影響する?
退職代行の利用は、経歴として残りません。そのため、転職への影響はないといえます。
ただし、以下のような場合は転職先に退職代行の利用がバレるかもしれません。
- 同業種に転職する場合
- SNSで発信してしまった場合
- 転職先の面接で言ってしまった場合
上記に気を付けてさえいれば、退職代行は安心して利用できます。どうしても不安な場合は、弁護士が運営している退職代行サービスを利用しましょう。法律により守秘義務が課せられていれば、情報が漏れてしまう心配はありません。
即日で退職できる?
結論、退職代行を使えば即日退職が可能です。本来退職には原則2週間必要となりますが、退職代行サービスを利用すればすぐに対応してもらえます。
ただし、実際の退職日が2週間後になってしまうケースは多いです。というのも、法的に労働者の意志で退職を進められるようになるまでの期間として、2週間が必要になります。
上記のことから、退職するには勤務先への通知が大切です。実際、退職の意志を伝えてしまえば、そこからは有給消化扱いにしてしまえば問題ありません。
万が一就業規則で「1か月前の通知が必要」のような記載があっても、法律の方が優先されることは理解しておきましょう。
退職代行を使う人はクズ?
退職代行を使う人は、決してクズではありません。そもそも退職代行を利用する時点で、会社側に何か問題があると考えられます。
仮に問題がなかったとしても、退職は労働者の権利です。また、退職に時間がかからないため、キャリアを無駄にしなくて済みます。
退職代行を利用するメリットは数多いため、自分だけで退職を進めるのが難しい場合は、積極的に利用しましょう。
追加費用が発生する場合はある?
基本的に、退職代行を使って追加費用が発生することはありません。しかし、以下のような場合は追加費用がかかることもあります。
- 退職の交渉以外の業務が発生した
- 退職が上手くいかずに裁判となった
- 労働組合が運営している退職代行サービスを利用した(労働組合費)
追加費用が不安な場合は、利用する前に必ず費用面を確認しておきましょう。基本的に弁護士が運営している退職代行サービスに限られますが、確認しておかないと後々高額な請求となる可能性があります。
退職金の計算方法は?
退職金は大きく分けて4種類に分かれます。それぞれの計算方法については、以下の表を参考にしてください。
| 種類 | 計算方法 |
| 退職一時金 | 定額制:勤続年数に応じてあらかじめ支給額を決定
基本給連動型:勤続年数と退職時の基本給をもとに退職金を計算 ポイント制:基本給・勤続年数・役職・退職理由などをポイントにして決定 別テーブル制:勤続年数に応じた基準額と役職係数などを表にして決定 |
| 確定給付企業年金 | 掛金月額と納付月数、利回りに応じて決定 |
| 中小企業退職金共済(中退共) | 基本的に掛金月額と納付月数をベースに計算 |
| 企業型確定拠出年金(DC) | 定期預金・保険投資信託などの金融商品から任意で選択し、投資配分を決めて運用。その結果に応じて退職金を計算 |
退職金の受け取りを希望するなら、自社がどの種類に当てはまるかを必ず確認しておきましょう。
中小企業の退職金の相場は?
中小企業の退職金相場は、学歴や勤続年数・退職の理由で異なります。退職金の額が気になる人は、以下を参考にしてください。
| 勤続年数 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 定年 |
| 自己都合による退職 | 大卒:約112万円
短大・専門卒:約98万円 高卒:約90万円 |
大卒:約212万円
短大・専門卒:約183万円 高卒:約170万円 |
大卒:約343万円
短大・専門卒:約292万円 高卒:約272万円 |
大卒:約490万円
短大・専門卒:約423万円 高卒:約397万円 |
大卒:約653万円
短大・専門卒:約565万円 高卒:約532万円 |
– |
| 会社都合による退職 | 大卒:約149万円
短大・専門卒:約123万円 高卒:約122万円 |
大卒:約265万円
短大・専門卒:約227万円 高卒:約214万円 |
大卒:約414万円
短大・専門卒:約346万円 高卒:約328万円 |
大卒:約578万円
短大・専門卒:約493万円 高卒:約465万円 |
大卒:約754万円
短大・専門卒:約645万円 高卒:約604万円 |
大卒:約1,091万円
短大・専門卒:約983万円 高卒:約994万円 |
引用:退職金の種類と計算方法は?退職金の種類やかかる税金についても解説
具体的な退職金については、勤め先の就業規則・退職金規定を確認してください。
退職代行サービスを利用しても退職金はもらえる!
今回は、退職代行サービスを使った場合に退職金をもらえないケースや、不支給や減額を防ぐ対応策について解説しました。
退職代行を利用した場合でも、会社の就業規則に退職金規定が記載されており、支給条件を満たしていれば受け取れます。しかし、退職金制度を導入していない企業や支給の条件を満たしていない場合は、退職金はもらえないので注意しましょう。
ぜひこの機会に、EXITの退職代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
特集
インタビュー
やめ知識
-
やめ知識
仕事辞めたい、もう疲れた…30代が仕事を辞めたいと悩む7つの理由!対処法とよくある疑問を解説
-
やめ知識
試用期間中に退職したいけど難しい?退職理由や納得されやすい伝え方を紹介!
-
やめ知識
仕事辞めたい、、疲れた20代・新卒が仕事を辞めたい場合の対処法は?会社に疲れた時の退職すべきかの判断基準
-
やめ知識
【仕事を辞めたい40代必見】仕事を辞めたい原因と対処法、体験談も紹介
-
やめ知識
退職代行で辞めた人は後悔する?リアルな口コミと後悔しない使い方
-
やめ知識
休職のまま退職はできない?復職せずに円満に辞めるコツを紹介
-
やめ知識
試用期間中に即日退職できる?確実にすぐ辞める方法や注意点も紹介!
-
やめ知識
入社してすぐ辞めるのはあり?円満な退職理由や保険料についても紹介
-
やめ知識
HSPで仕事を辞めたい…辛くて限界のサインや理解してもらえる退職理由
-
やめ知識
退職を伝えてから実際に辞められるまでの期間は何ヶ月前?2週間と言われる理由や円満退職のコツ
-
やめ知識
即日可能?バイトを今すぐ辞めたい時に使える理由や辞めるためのポイント
-
やめ知識
事務職を辞めたいと思う瞬間は?つらくて退職したい時の対処法やおすすめ転職先
-
やめ知識
退職代行のトラブル事例10選!確実に失敗しない方法と具体的なトラブル回避策を解説
-
やめ知識
退職代行は裏切り・無責任?頭がおかしいと言われる理由や対策について解説
-
やめ知識
【ありえない?】退職代行とは?サービスのメリット・デメリットや退職までの流れ
-
やめ知識
上司に退職をメールで伝えるのはあり?申し出の文例や注意点も紹介
-
やめ知識
【営業を辞めたい人必見】営業職のよくある悩みや対処法、転職時のコツも紹介
-
やめ知識
【辛い・もう限界】仕事を辞めたい原因とストレス解決方法を紹介!
-
やめ知識
会社を辞めたい…つらいと感じる理由や対処法、仕事を退職するリスクも紹介
-
やめ知識
仕事を辞めたいと感じる10つの理由と対処法!辞める判断基準も紹介
-
やめ知識
退職代行サービスの金額相場を徹底解説|弁護士への依頼は必須ではない!?